Seminar & Writing - セミナー・執筆活動

居住用の区分所有財産:区分所有補正率の適用にあたり判断に迷うケースについて
2025.10.07
近年、高層タワーマンションの相続税評価額が実勢価格に比べ著しく低いことに着目した「タワーマンション節税」と呼ばれる相続税の節税スキームが広がり問題視されていました。このため、令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)については法改正がなされ、従来の評価額をベースに居住用区分所有財産に係る区分所有補正率(以下「区分所有補正率」という)を乗じるという評価方法が導入されました。
本評価方法が導入されてから1年以上経過し様々な評価事例が出てきましたが、中でも判断に迷う2つのケースを以下に取り上げます。
1. 「敷地面積」の判定:マンションの敷地内に複数棟の建物が建ち路線価が付されている道路で分断されているケース
広大な敷地に複数棟の建物が建ち、そのうちの一棟に被相続人が居住しているものの、敷地権が敷地全体に及ぶケースがあります(下図参照)。このような土地を評価する場合は、A~Dをそれぞれ一利用単位の土地として評価し、それぞれの価額に敷地権割合を乗じた合計額が相続税評価額となります。
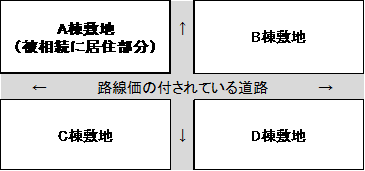
この場合、区分所有補正率の計算上の「敷地面積」は、敷地権が及ぶ全体の合計地積(A~Dの合計値)を用いるのでしょうか。それとも被相続人が居住しているA棟の敷地面積のみが対象になるのでしょうか(参照:末尾記載「居住用区分所有財産に係る区分所有補正率の計算明細書」D⑥欄)。
直接的な公的見解はありませんが、令和6年5月14日付資産評価企画官情報第2号「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A(問5)」によると、次のように示されています。
一棟の区分所有建物の敷地の面積は、原則として、利用の単位となっている1区画の宅地(評価単位)の地積によることとなります。ただし、例えば、分譲マンションに係る登記簿上の敷地の面積のうちに、私道の用に供されている宅地(歩道上空地などを含みます)があった場合でも、その宅地の面積を含んだ登記簿上の敷地の面積によることとしても差し支えありません。他方で、例えば、分譲マンションの敷地とは離れた場所にある規約敷地については、この一棟の区分所有建物の敷地の面積には含まれません。
さらに、ただし書き以降の部分に関しては、以下のような趣旨が示されています(令和5年10月1日付資産評価企画官情報第2号)。
評価乖離率に基づき評価することとした理由の一つが、申告納税制度の下で納税者の負担を考慮したものであるから、同様の趣旨により、納税者自身で容易に把握可能な登記簿上の敷地の面積によることとしても差し支えない。
以上を整理すると、次のようになります。
① 原則的には1区画の宅地(評価単位)の地積による
② -1.私道の用に供されている宅地については敷地面積に含めて差し支えない
-2.駐車場等、マンション敷地から離れたところにある規約敷地は除外する
③ 納税者自身で容易に把握可能な登記簿上の敷地面積を用いることも認められている
上述のQ&Aを勘案すると、他棟の敷地について明示的な規定はありませんが、敷地権がA~D全体に及び、通常は一体的に管理・使用されるケースですので、合計面積を基礎とするのが自然と考えられます。
したがって、区分所有補正率の計算明細書における敷地面積は、A棟~D棟の敷地の合計面積を基にするのが相当であると考えます。
2. 相続税評価額が0円になるケース:区分所有補正率が「評価しない」となる場合
区分所有家屋とその敷地を評価するにあたり、相続税評価額に乗じる区分所有補正率は、評価乖離率となるか、1.0つまり「補正なし」となるケースがほとんどです。
しかし、稀に評価乖離率が0または負数となるケースがあります。その場合、相続税評価額に区分所有補正率を乗じることなく、「評価しない」とされます。
つまり、相続税評価額が0円となることとされています。
このことは計算明細書の(注5)や国税庁の「居住用区分所有財産の評価に関するQ&A」問2(注1)にも記載されています。
「評価しない」となるケースは、敷地面積が広大である、築年数が古いといった場合です(末尾「居住用区分所有財産に係る区分所有補正率の計算明細書」参照) すなわち、例えば同じマンションでも、令和5年12月31日発生の相続では従来どおり評価額が算定される一方、令和6年1月1日発生の相続では「評価しない」となり、土地・建物ともに評価額が0円になるという事態が起こり得ます。 この点については、実際に売買価格がつく以上、0円は不合理であり、何らかの価額を計上すべきとの見解もあります。しかし、現行通達が「評価しない」と定めている以上、0円評価となると解されます。
もっとも、令和6年5月14日付資産評価企画官情報第2号「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A(問9)」には次のような補足があります。
「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる場合には、評価基本通達6項により、個々の財産の態様に応じた適正な時価評価で評価する。」
したがって、例えば相続税の申告期限までに売却予定で、かつ売却額が確定している場合には、その売却額で評価すべきと考えます。
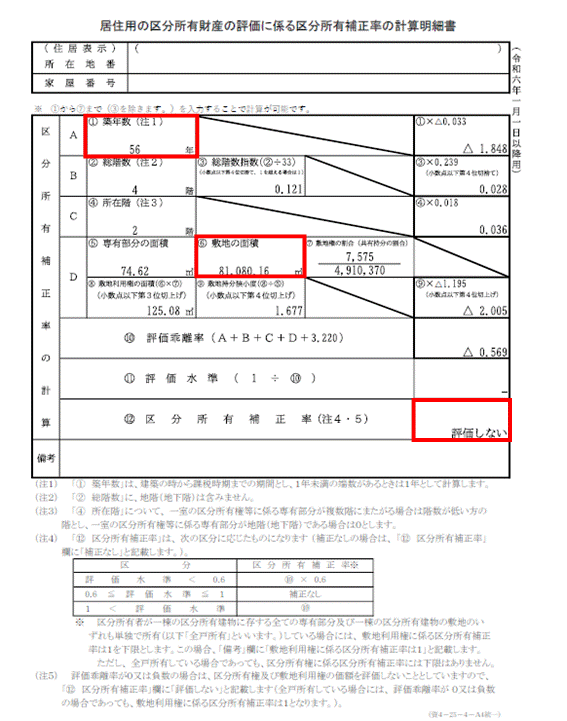
(竹中暢子)
当サイトに掲載の文章等の無断転載を禁じます。
全ての著作権は株式会社YUIアドバイザーズに帰属します。
無断使用、無断転載が発覚した場合は法的措置をとらせていただきます。
